心理・チュートリアル通信「実力診断テスト活用法」(3)
2025年度
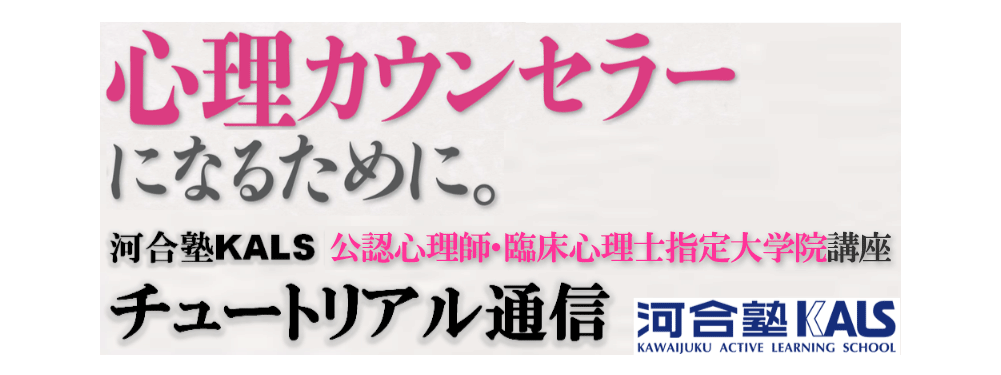
チュートリアル通信では、大学院に合格したKALSのチューターが、勉強法や参考図書、研究計画書について、各大学院の様々な情報や、心理士事情など皆さんに有益となるようなコンテンツをお送りしていきます。日々の勉強の合間の息抜きとして、是非ご覧になってみてください。
直前期はこれをしよう!
新宿本校チューター:大澤
皆さん、こんにちは!新宿本校チューターの大澤です。今年も暑いですね。追い込みに入っている方も多いかもしれませんが、水分補給、睡眠、栄養を大事に、健康第一で乗り切りましょう!
今回は「実力診断テストの活用法・直前期対策」についてお話します。ぜひ気になる部分をピックアップしてご覧ください。
目次
1.実力診断テストの受験
2.実力診断テストの振り返り
3.直前期①これまでの総復習
4.直前期②志望校対策
5.直前期③面接対策
6.直前期④超直前期
1.実力診断テストの受験
皆さん、実力診断テストを受験されましたか?受験された方は、入試当日の緊張感、時間制限の中でなんとか答えを導き出す頭の使い方、全体の時間配分等、とても有意義な経験となったことと思います。
また、中には「まだ自分の実力が足りていない」、「他にやらなければならない勉強が多くて手が回らない」などの理由で取り組んでいない方もいるのではないでしょうか。KALSの実力診断テストはとても良質な問題が揃っていて、これまでの講義の総復習をするのにちょうど良いレベルの内容です。もし提出期限に間に合わなくてもぜひ取り組んで、解答を見て自己採点してみてください。
2.実力診断テストの振り返り
実力診断テストに取り組んだら、必ず振り返りをしましょう。正解できた問題も、不正解だった問題も、解答解説やテキスト、ノートを見て知識をしっかり頭に叩き込み直します。特に不正解だった問題について、問題のどういった文言に引っかかったのか、どこの知識が不十分で正解できなかったのか分析することが大切です。また、全体的な傾向も見てみましょう。一般的な心理学用語の知識、人物名、論述など、どのような出題形式が得意、不得意なのかを分析します。さらに、解答解説を見ると領域ごとに何点取れたのか、その領域では他にどのような重要単語があるのかが分かるようになっています。これを活用しない手はありません。ぜひとも、自分の得意分野・苦手分野を把握し、残り少ない入試対策時間を効率よく進めていきましょう。偏差値や得点分布による自分の位置に一喜一憂されている方もいるかもしれません。しかし、まだ時間はあります。あくまで診断テスト受験時の成績であり、入試までに足りないところを埋めていけば良いのです。プラスに考えて利用していきましょう。KALSの持つ経験値やデータは圧倒的に信頼のおけるものです。心理学では、このテストに出題されているものは全て入試に出題されると考え、マスターするつもりで復習しましょう。心理英語では、知らなかった単語を暗記し、英文の訳を確認してどのように訳されているか学ぶことも大切です。
但し、実力診断テストだけにこだわり過ぎる必要はありません。上記をこなしたら、通常の受験勉強へ切り替え、時間を有効活用していきましょう。
3.直前期①これまでの総復習
直前期には、これまで学んできたこと全体を総復習していきます。志望校で出題されやすい領域に力を入れつつ、出題される可能性のある範囲全体に漏らさず目を通すことも大切です。ノート作りをしてきた方はノート全体を見直しましょう。心理学では、出題されやすい領域から、ノートの下スペースにその単語の用語説明を改めて書いてみると力がつきます。心理英語では、毎日一問は訳すと決め、問題演習に取り組むと共に、これまで覚えてきた心理英単語を定着させるよう繰り返し暗記に励むと共に、新しい英文で出会った単語があればどんどんインプットしていきましょう。心理統計学では、過去問の類題に多く取り組みましょう。論述対策では、これまでに先生方に添削して頂いた論述を読み返したり、解答例の論述や解説を読み直したりすると共に、少なくとも一日一問は論述問題に取り組めると良いでしょう。KALSの直前講習では過去問の解説など、入試に直結した内容が取り扱われます。私も実際、入試で直前講習の内容が複数出題されました。ぜひ受講するようにしてください。
4.直前期②志望校対策
KALSテキストや自分の参考書の全範囲の勉強を終わったときに、志望校で過去に、それでも網羅できていない問題が出題されていると気付くこともあるでしょう。この時に役に立つのが「志望校対策ノート」です。ノートを1冊用意し、過去にその学校で出題された、テキストに載っていない範囲の用語についてまとめていきます。1用語300~400文字位でその用語についてまとめていきましょう。この時、全般的なテキスト・参考書に載っていない知識は、自分で書籍から調べる必要があり、どんな本にそれが載っているかを見つけ出すことが大切です。一般的には、その大学の出題者の先生が書かれた本に答えが書いてあります。そうした書籍は、その大学や大学院の講義の教科書として使われていることも多く、公開されているシラバスを見ると書籍名についての情報も入手できます。本を入手したら、出題された用語やその周辺の用語についてまとめておいて、似たような問題が出題されても対応できるように準備を進めます。志望校の先生が書かれた本を学ぶことはそのまま面接などで志望動機に結び付けることも可能ですし、大学院の授業の予習にもなりますのでぜひ行うことをお勧めします。
5.直前期③面接対策
直前期の面接対策として、まず、質問回答集を作ります。面接で質問されそうな問いを書き、その下に実際に面接でどう答えるかを考え、理想の答えを書きます。この時、箇条書きや体言止めではなく、実際に面接で話すときの口調で書きましょう。面接で質問されやすい質問は以下の通りです。これらについては、聞かれたらすぐに答えられるよう答えを準備しておきましょう。
- 大学院の志望動機
- 他校ではなく、その学校を選んだ動機
- 大学院修了後の希望進路
- どのような心理臨床家になりたいか
- どのような研究を行いたいか
- 心理学に興味を持ったきっかけ
- 関心のある心理学の領域
- 卒業論文の内容
- 研究計画書についての説明、特にそのテーマに興味を持った理由
- 臨床心理士(公認心理師)しか取れないが、それでも大丈夫か(該当する人のみ)
- 社会人やアルバイトの経験をどのように生かしていくか
- 他学部・他領域出身の場合、なぜ心理学に転向したのか、他領域での学びをどのように今後に生かせるか。
質問回答集は何度も読み直して直前まで吟味を重ね、ベストな答えを作っていきましょう。もちろん、これ以外の質問が来ることもありますが、安心して答えられる質問が多ければ、意外な質問が来ても落ち着いて対応できます。回答集が出来上がったら練習を行います。チューターカウンセリングで模擬面接ができますのでぜひご活用ください。家族や友人などに協力してもらうことも効果的です。それらが叶わない場合でも、声に出して話してみる練習はぜひ行いましょう。
6.直前期④超直前期
試験会場へのアクセスを確認し、可能であれば下見に行くのも良いでしょう。当日の試験時間と同じスケジュールで過ごしてみることで、試験のイメージを作ることも有効です。着ていく洋服(面接ではスーツ)、受験票、筆記用具、交通費、昼食、直前に見直したいノートや参考書、面接質問回答集、英語辞書、持って行きたいお守り・軽食など、準備に余念がないようにしましょう。複数校受験される場合でも、直前にはその受験校が第一志望であるような心構えを作って、絶対に合格すると心に決めて臨みましょう。交通機関の遅延も多いので、時間には余裕を持って行動できるよう当日のスケジュールを考えましょう。準備には意外と時間がかかるものです。前日の就寝時間が遅くならないよう、早めに当日の準備をしておきましょう。
入試当日まで、悔いなくやりきることが大切です。1分でも時間が合ったら何か覚えるつもりで、時間を大切に過ごしましょう。詰めが甘くならないよう一つ一つ丁寧に復習し、随時、知識の補充をしていきます。同時に体調管理も重要です。直前期は睡眠時間をしっかり確保していけるよう、何事も早め早めの準備を心がけてください。皆さんのご健闘をお祈りしています。

