心理・チュートリアル通信「実力診断テスト活用法」(2)
2025年度
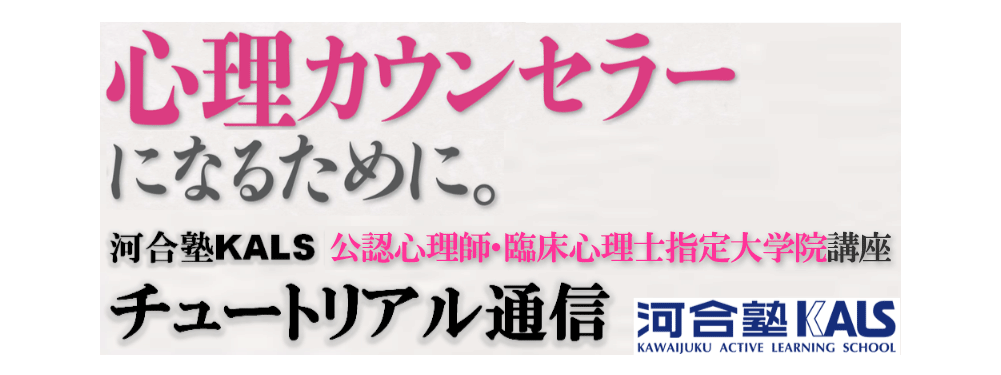
チュートリアル通信では、大学院に合格したKALSのチューターが、勉強法や参考図書、研究計画書について、各大学院の様々な情報や、心理士事情など皆さんに有益となるようなコンテンツをお送りしていきます。日々の勉強の合間の息抜きとして、是非ご覧になってみてください。
実力診断テストの活用方法
名駅校チューター:村木
こんにちは、名駅校チューターの村木です。
みなさん、暑い夏をどのようにお過ごしでしょうか?暑さで体調を崩しやすいかもしれませんが、水分補給を大事にして試験に向けて体調を整えていきましょう!
今回は、実力診断テストの活用方法についてお話ししたいと思います。
みなさん、実力診断テストの結果はいかがでしたか?良い結果だった人も、思うようにいかなかった人もいると思います。でも大丈夫、本番はまだこれからです。今回の結果をこれからの勉強に活かしていきましょう!
ですが、どのように活かしていけばよいか、試験までどんな勉強をすればよいか迷っている方もいると思います。そこで、私自身がこの時期に行っていた活用法をご紹介します。ぜひ、参考にしてみてください!
1.間違えた問題の見直し
まずは、テストが返ってきたら間違えた問題の見直しです。ただ解答を見て写すだけではなく、どうして間違えたのか、どこまでは理解できているのかを考えながら丁寧に見直すことが大事だと思います。また、間違えた問題だけでなく、明確には分からなかったけれど正解できた問題の見直しもしていました。これをやることで、自分の曖昧だった知識や理解をはっきりさせ、定着につなげることができると思います。
2.得意な分野と苦手な分野の把握
次に、自分自身の得意な分野と苦手な分野についての把握です。実力診断テストでは、個人成績表が結果と一緒に返ってきます。ここには、KALS内での順位が載っていて一喜一憂するかもしれません(恥ずかしながら、私自身がそうでした…)。しかし、大事なポイントは、心理学の分野別評価と内容別評価、心理系英語の内容別評価を確認することだと思います。分野別に分かれているので、それぞれ自分が得意なのか苦手なのかを把握しやすいです。また、自分の志望校に出やすい分野との比較をしておくことで、志望校別の対策も行いやすいと思いました。
3.モチベーションの材料にする
今回のテストの結果は、単なる点数ではなく、みなさんの今までの学習状況が反映された記録だと思います。思うような点数が取れなかったときこそ、自分の努力や足りなかった部分を振り返る機会です。例えば、「全然覚えられない…」と思っていた分野で、数問でも正解できていたなら、それは着実に知識が積み重なっている証拠です。その実感が、自信とやる気に変わります。また、「今のままじゃダメだ」と感じたなら、それは次の行動を起こすエネルギーになります。どんな感情も、向き合い方次第でモチベーションの材料になると思います。
今回は、実力診断テストの活用法として、私が行っていたことを紹介させていただきました。焦りや不安もあるかもしれませんが、着実に前へ進めば、必ず結果はついてきます。今回のテストでうまくいかなかった人も、むしろそれは「ここから伸びる余地がある」ということだと思います。努力はすぐには形にならないこともありますが、正しい方向に向けて積み重ねていけば、確実に力になります。
だんだんと試験が近づいてくる中、ふと不安になることもあるかと思います。そんなときは、いつでもチューターに相談してください。一緒に最後まで駆け抜けていきましょう!

