心理・チュートリアル通信「実力診断テスト活用法」(1)
2025年度
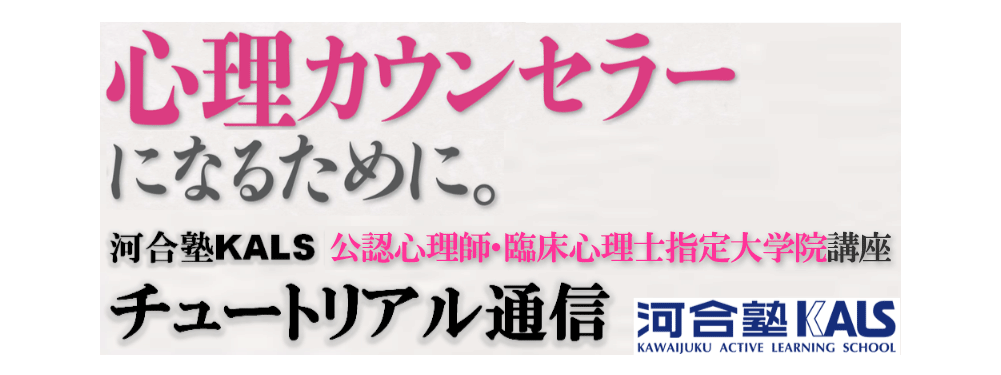
チュートリアル通信では、大学院に合格したKALSのチューターが、勉強法や参考図書、研究計画書について、各大学院の様々な情報や、心理士事情など皆さんに有益となるようなコンテンツをお送りしていきます。日々の勉強の合間の息抜きとして、是非ご覧になってみてください。
実力診断テスト
新大阪校チューター:中島
こんにちは。新大阪校チューターの中島です。
今回は,実力診断テストを受験された方を対象に,テスト結果の分析および活用方法について整理していきたいと思います。
(1)知らなかった用語の知識をインプットしよう
今回の実力診断テストで,いくつ「知らなかった用語」に出会えたでしょうか。「知らなかった」には様々な段階があると考えられます。例えば,①まったく回答できなかった,②聞いたことはあるが回答できなかった,③回答したが正答ではなかった,など。これらの用語はすべて「知らなかった用語」として素直に受け止め,復習するようにしましょう。1度出会った用語は,次からは必ず完答する!それぐらいの気持ちでやっておけば,本番も安心です。
復習方法はシンプルに,いつも使っているノートや単語カードなどに追加する方法でいいと思います。注意点としては,内容をまとめるときに,テストの回答例を丸写しにしないようにしましょう。回答例はテスト用にスリム化された文章表現になっています。せっかくですので,回答例だけでなく,KALSテキストやインターネットで用語を調べてみてください。文や言葉だけでなく,図やイラスト,日常における具体例なども一緒にメモしておくと,より意味のある記憶になると思います。
(2)自分の弱点を探そう
科目や分野ごとに正答率を比較して,自分の得意あるいは弱点を探してみましょう。特に「弱点」の発見は早めがおすすめです。以下にいくつか比較の観点をあげてみたいと思います。
英語vs心理学
こちらはすでに比較されているかもしれませんが,各科目の順位などはいかがでしたでしょうか。もしどちらかが極端に低い場合は,学習の時間配分を変更する必要があるかもしれません。(ただし,志望校の科目配点に大きな差がある場合は,弱点の克服よりも,配点の高い科目を優先した方がよいでしょう)
また,科目間のバランスがよかった人も油断は禁物です。多くの受験生が,心理学の知識をインプットし終えたころに,ぐんっと英語が読めるようになるという傾向があります。ライバル達の成長を考慮して,自分自身の英語対策がおろそかにならないようにしておくとよいでしょう。
分野ごと
次に,分野ごとの正答率を比較してみましょう。ここでいう分野とは,例えば「神経生理」「学習」「発達」「知覚」…などのことです。特定の苦手分野はあるでしょうか。苦手分野があり,なおかつその分野が志望校の過去問でも出題されている場合は,急いで対策をしましょう。可能な人は,苦手分野の講座動画をもう一度視聴してみるのもよいかもしれません。
よくあるパターンとして,「発達や臨床分野は,もとから関心があって得点も取れているけど,神経生理や学習は知識が浅く,学習意欲もあがらない…」といったお悩みをうかがいます。たしかに,心理職のイメージからすると神経生理や学習分野は縁遠いような感じがするかもしれません。ですが,これらの分野は医療や教育現場で働く場合,もっともよく使う知識でもあります。もし学習意欲があがらない苦手分野があるなら,その分野が現場でどのように活用されているのか,先生やチューターに尋ねてみると意外な発見があるかもしれません。
(3)部分得点もしくは減点のパターンを分析しよう
最後に,答案用紙の中で,完答でも無回答でもなかったところ,つまり部分得点や部分減点があった箇所に注目してみましょう。あなたの回答は,どんな方法で部分得点を得ていますか。また,何が理由で部分減点となっていますか。
特に,1点の差をあらそう入試においては,部分得点の取り方を心得ていることが重要です。「この一文で2点もらえるのか…」ということがある程度分かっていれば,本番でも同じようにねばることが可能です。よく知らない用語が出てきたとしても,白紙ではなく,少しでも関連する内容を書いて部分得点を1点でもつかみ取る。そういうことが,できているのか,できていないのか,改めて答案用紙を確認してみてください。
反対に,部分減点があった箇所についても,その理由をおさえておきましょう。よく見られるのは,①内容としてはいいが,日本語の構成に誤りがある(例:主語と述語が対応しない,誤字脱字),②知識量が乏しく,文字数が不足している,③専門用語を正しく用いておらず,稚拙な表現になっている(例:オノマトペや口語表現の多用,情動/感情/気分を混同した表現)などのパターンがあります。①の場合は,自分にその傾向があると知っているだけでも,ミスの軽減につながります。また,試験の最後に見直しの時間を取れるよう時間配分をすることで,もったいない減点をずいぶんと減らせることでしょう。②と③の場合は,どちらも関連用語の知識不足が要因にあると考えられます。この時期は,1つ1つの用語についての知識は蓄積されつつあると思うので,今度は知識と知識のつながりを意識して,まとめてみるのもおすすめです。例えば,以下のようなキーワード・マップを作ってみる方法があります。

このように,これまで学んだ用語を俯瞰的に図で整理してみます。用語と用語の関連が見えてくると,回答欄の2行目,3行目に書くことが自然と出てきやすくなるのではないでしょうか。ポイントは,レイアウトにこだわらないことです。あとでまた描き直せばいいやの精神で,まずは「線でつなげてみる」ことを意識して整理してみてください。
以上,今回は実力診断テストの分析および活用方法について整理してみました。
いかがでしたでしょうか。
いよいよ入試直前期に入り,残りの時間で「何をやるか」がますます重要になってきますね。そんな時期だからこそ,テスト結果を客観的に分析し,学習内容を軌道修正することがもっともタイムパフォーマンスがよい方法と言えるでしょう。
ぜひもう一度,採点済みの答案用紙を開いてみてください。あなたが合格をつかむためのヒントが,そこに隠されていると思います。
最後までお読みいただき,ありがとうございました。

