心理・チュートリアル通信「論述対策」(2)
2025年度
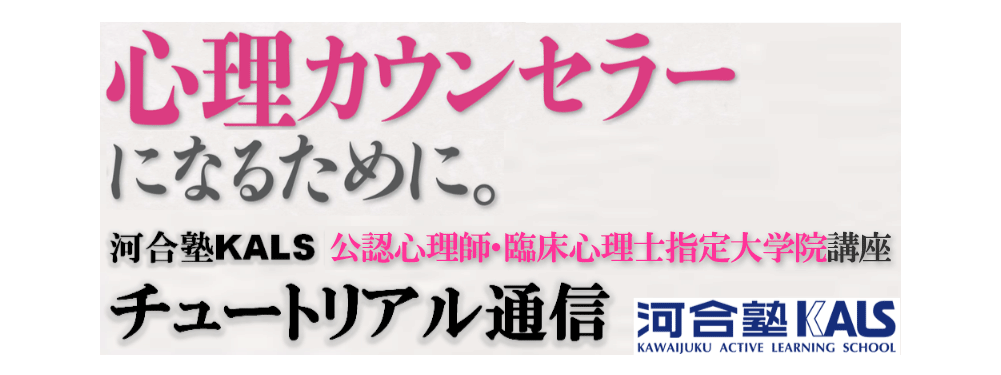
チュートリアル通信では、大学院に合格したKALSのチューターが、勉強法や参考図書、研究計画書について、各大学院の様々な情報や、心理士事情など皆さんに有益となるようなコンテンツをお送りしていきます。日々の勉強の合間の息抜きとして、是非ご覧になってみてください。
「論述対策」について
名駅校チューター:河合
みなさん、こんにちは。KALS名駅校チューターの河合です。
今回は、私自身の経験を交えながら「論述対策」についてお話しします。
「論述試験なんて、自分に突破できるのだろうか……」と、私も最初は論述練習に対して不安が大きく、なかなか一歩を踏み出せませんでした。でもある時、「書き慣れていないだけなんだ」と思えるようになり、モチベーションが上がったことを覚えています。論述は受験のためだけでなく、その後の自分の力になる——そう考えられるようになると、気持ちも前向きになりました。
日々の勉強を通して、みなさんの知識は確実に積み重なっています。次のステップとして、それを「自分の言葉で表現する力=アウトプット力」にしていきましょう。教科書的な知識を、自分の言葉で言い換える練習を重ねることが大切だと思います。
私が実践していた論述対策としては、以下のようなことがあります。
・下書きをせずに、いきなり書き始める練習
最初はかなり苦痛でしたが、繰り返すうちに徐々に慣れていきました。特に、苦手なテーマや用語は意識的に何度も取り組んでいました。
・問いにきちんと答えられているかの確認
授業でもよく言われますが、「何を問われているか」をしっかり意識して答えることが重要です。
・論述の授業にできるだけ欠かさず出席すること
書けないときは出席するのがつらく感じることもありますが、そういう時こそ踏ん張りどころだと思います。
・論述添削の積極的な活用
思うように書けず、提出をためらってしまうこともありましたが、今振り返ると、どんどん添削に出してフィードバックを受けた方がずっと効率的だったと感じます。
また、最初から一人で完成度の高い論述を書くのは難しいことではないでしょうか。大切なのは、「わかっているつもり」を少しずつ減らしていくことではないかと思います。実際に書こうとすると手が止まってしまったり、暗記していたはずの内容がうまく説明できなかったりすることもありました。そんな経験から、理解を深めるためには、誰かに説明するようなつもりで練習を重ねることが必要だと感じました。私自身、最初は理解があいまいな部分が多く、思うように書けないことばかりでした。それでも練習を続けていくうちに「論述とは、わかりやすく伝えること」、そして「伝えたいことが相手にしっかり伝わること」が最も大切だと気づきました。これは、将来心理職として求められる力にもつながるのではないかと思います。授業中に耳にした「論述はラブレター」という言葉も、とても印象に残っています。自分の理解を相手に伝わる形で表現できるよう、ぜひ練習を積み上げていってください。
手書きの練習にもぜひ取り組んでください。本番の試験は手書きで行われます。パソコンで文章を書くときと比べて、手書きには時間や体力的な負荷も伴います。実際の試験を想定して、時間を計って手書きする練習をしておくと良いと思います。また、いきなり長文を書こうとするのは大変なので、私の場合はまず200字程度や、300~400字の短めの文章から練習を始めて、少しずつレベルを上げていきました。
最後に、論述で大切なポイントは主に二つあると思います。一つは「問いに的確に答えること」、もう一つは「論理が飛ばないこと」です。論述練習は、継続と不安との闘いでもあります。思うように書けなかったり、周囲と比べて落ち込んだりすることがあるかもしれません。納得のいく文章が書けないまま練習を続けることに苦しさを感じることもあるかもしれません。それでも、あきらめずに(無理をしすぎずに)続けていれば、ふっと書くことが楽になる瞬間がやってくると思っています。
みなさんの努力が実を結ぶよう、心から応援しています。困ったときには、ぜひチューターカウンセリングも活用してみてください。

