心理・チュートリアル通信「学習のペースをつかもう & KALSの活用法」
2025年度
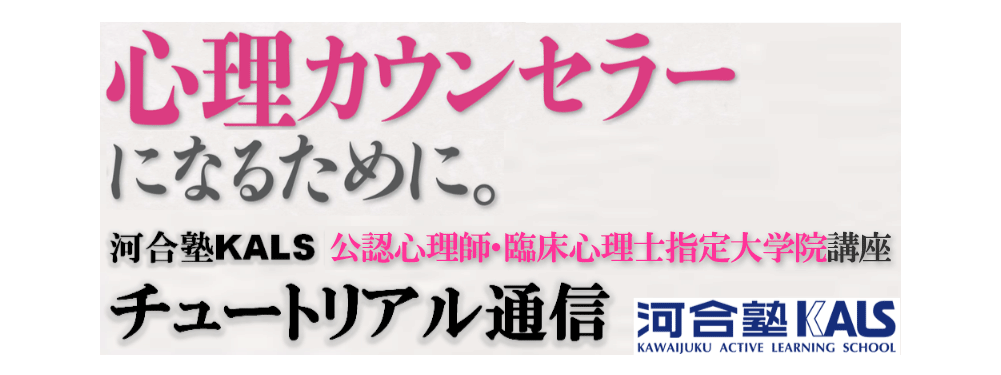
チュートリアル通信では、大学院に合格したKALSのチューターが、勉強法や参考図書、研究計画書について、各大学院の様々な情報や、心理士事情など皆さんに有益となるようなコンテンツをお送りしていきます。日々の勉強の合間の息抜きとして、是非ご覧になってみてください。
学習のペースをつかもう & KALSの活用法
新大阪校チューター:中島
こんにちは、新大阪校チューターの中島です。
新年度が始まり、みなさんいかがお過ごしでしょうか。私は元KALS受講生なのですが、当時の今頃といいますと、受験勉強をいざ始めたものの、どのように進めていったらよいのか自信が持てず、フワフワしたような気持ちで生活していたように思います。そこで今回は「学習のペースをつかもう&KALSの活用法」というテーマで、ペースメイキングのコツや、ぜひ活用したいKALSのサポートシステム等についてご紹介したいと思います。私自身の体験もふまえての内容になりますので、よかったら参考にしてみてください!
◆週間スケジュールをたてよう
まず、曜日ごとに何をするか決めておきましょう。通学生の方は講座の曜日が決まっているので、講座に出席することを最優先にして、他の曜日のスケジュールを組むとよいでしょう。オンライン生の方も、できれば各講座を視聴する曜日や時間は固定するほうが個人的にはよいと思います。なぜなら、“空いた時間に少しずつ進める”という方法は、どうしても学習進度が遅れがちになるためです。一度にインプットできる知識の量には限度があるため、入試直前にあわてて詰め込むといったことは、とてももったいないです…。まずは「1週間で各講座1つずつ進める」等の具体的なペースを設定し、それを維持していきましょう。
また、講座と同じぐらい大切なのが「アウトプット」です。覚えたことを書き出したり、問題を解いたりするといったアウトプットがなければ、残念ながら知識は定着しません。したがって、講座で得た新しい知識をアウトプットする時間を週間スケジュールの中に確保しておきましょう。アウトプットの仕方は、自分に合った方法でよいと思います。私の場合は、講座を受けた翌朝に、復習ノートに内容をまとめるといったことをしていました。記憶がホットなうちに復習する方が、個人的には効果があった感覚があります。また、講座によっては課題や小テストを実施してくださる場合もあるかもしれません。そうした問題は終わった後も保管しておいて、忘れたころにまたやってみるのもおすすめです。
このように、「講座」「アウトプット」、さらには「英語の予習」「研究計画書作成」を1週間の中にそれぞれ配置したスケジュールを組んでみてください。
◆月間スケジュールをたてよう
週間スケジュールが決まったら、次は月間スケジュールについてもある程度設定しておきましょう。ここでいう月間スケジュールとは、入試日から逆算して、〇月までには〇〇をするといったノルマを定めたものになります。ご参考までに、受験生当時の私がたてたスケジュールは以下になります…。
【4月】 ・講座スタート・チューターカウンセリング(1回目)
【5月】 ・研究計画書(具体的なテーマ決定)・オープンキャンパス参加
【6月】 ・研究計画書(下書き完成)・研究室訪問
【7月】 ・研究計画書個別指導(1回目)・講座受講完了・模試
【8月】 ・研究計画書個別指導(2回目)・面接練習・出願
【9月】 ・入試
結果的には、このスケジュールは大幅にズレました(泣)
特に6月に予定していた研究室訪問は先方の都合もあるため、なかなか計画通りにはいきませんでした。これは多くの受験生が苦戦することでもあり、ある意味仕方のないことともいえそうです。
一方で、研究計画書の作成は、計画的に進めていく力が試されると感じます。研究計画書には少なくとも4か月程度はかかると思います。また、1人で急いで作成した計画書と、講師やチューターのアドバイスも取り入れながら時間をかけて練り上げた計画書とでは、一目見ただけでも完成度が全然ちがいます。月間スケジュールは、特にこの研究計画書をどのように完成に持っていくかという観点で立てられるとよいでしょう。
最後に、月間スケジュールを立てられたら、そのスケジュールで間に合うのか、もしくは無理しすぎていないかについて、チューターや先輩といった実際に大学院入試を経験した人に確認してもらうこともおすすめです。
◆チューター・カウンセリングを受けてみよう
月間スケジュールにもありましたように、研究計画書は受講生のみなさんと講師、チューターの3人4脚で進めていく方法がよいでしょう。特に、チューターには研究テーマを決めるスタートアップの段階から相談に行った方がいいと思います。なぜなら、自分一人で考えたテーマの場合、大学院生には難しすぎる、あるいは先行研究ですでに明らかになっているテーマになっている等の場合があるためです。途中でテーマを変更することは大幅な時間のロスになってしまいますので、4月の段階から、専門家の意見を参考にしながらテーマを決定していくとよいでしょう。
かくいう私はといいますと、はじめはどのように研究計画を書いたらいいのか全く分からない状態でしたので、受講してから毎週のようにチューター・カウンセリングを利用していました。チューターからもらったアドバイスで計画書の作成進度がぐんと上がりましたし、次回のカウンセリングまでにここまで書いて、チューターに見てもらおう!といったペースメーカー的な存在になっていたようにも思います。
もし、まだチューター・カウンセリングを受けたことがないようでしたら、ぜひ一度、試しに利用されてみてはいかがでしょうか。私の場合、研究計画書の相談に限らず、困ったときに相談できる顔なじみのチューターをつくっておくことは、精神的な支えにもなりました。ぜひご活用いただきたいサポートシステムの1つであると思います。
また、WEBでのカウンセリングに対応しているチューターもいます。特に遠方にお住まいのオンライン生の方にとっては,対話でコミュニケーションが取れる貴重な機会かと思いますので,ペースメイキングやモチベーション維持のため等々,どうぞお気軽にご予約ください。
◆まとめ
以上、「ペースをつかもう&KALSの活用法」についてご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。内容をまとめると、次のようなことがポイントとなります。
・講座は、できるだけ固定の曜日で進める
・講座を受けた後は、「アウトプット」を必ず行う
・研究計画書は入試日から逆算して、今から計画的に進める
・研究計画書は講師、チューターと3人4脚で作っていく
これらの内容が、少しでもみなさんのペースをつかむきっかけになれば幸いです。また、KALS活用法については、ここでは紹介しきれなかった他のサポートシステムもございます。したがって,何かお困りのことがある場合は,ぜひお気軽に校舎窓口のスタッフさんにお尋ね&ご相談いただくとよいと思います(お電話でもOKです)。
受験は“孤独な戦い”と言われることも多いですが、KALS受講生のみなさんにおいてはそうではありません。みなさんの周りにはKALSのサポート体制がたくさんありますので,ぜひそれらをフル活用していただき、いろいろな人の力を借りながら、1歩1歩進んでいってくださいね。最後までお読みいただきありがとうございました。

