心理・チュートリアル通信「研究計画をはじめよう」
2025年度
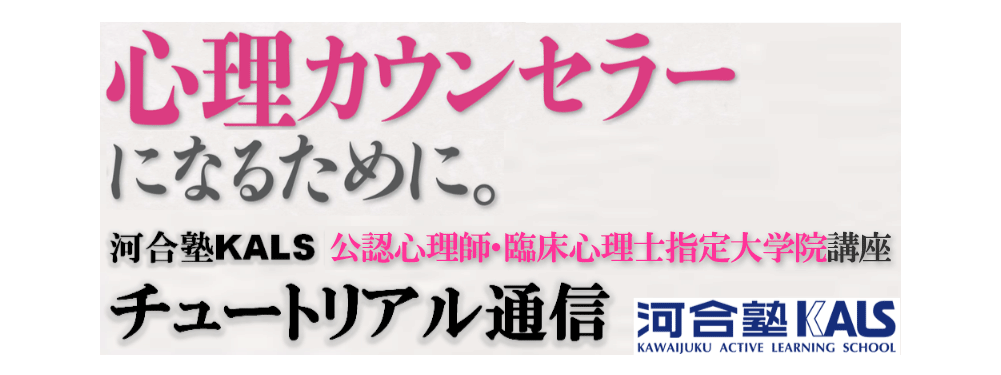
チュートリアル通信では、大学院に合格したKALSのチューターが、勉強法や参考図書、研究計画書について、各大学院の様々な情報や、心理士事情など皆さんに有益となるようなコンテンツをお送りしていきます。日々の勉強の合間の息抜きとして、是非ご覧になってみてください。
研究計画をはじめよう
新大阪校チューター:河合
こんにちは。新大阪校チューターの河合です。
今回は、研究計画書の作り方についてお話します。全文に目を通すには少し長いかもしれませんので、まずは目次をご覧いただき、必要だと感じられた項目を参照していただけますと幸いです。
目次
1.研究計画書とは
2.研究計画書の形式
3.研究計画書の作成手順
1.研究計画書とは
2.研究計画書の形式
3.研究計画書の作成手順
1.研究計画書とは
早速ですが、研究計画書とは、大学院で研究したい内容について示すものです。研究計画書は入試の合否の判断のひとつとなるため、筆記試験や面接と同じぐらい重要なものになります。
研究計画書は、志望校へ出願する資料のひとつとなります。そのため、志望校の今年度の募集要項が公表されていればそちらを、まだ公表されていなければ、とりあえず昨年度の募集要項を確認し、出願の締め切りを確認してください。まずは、研究計画書の完成目標時期を把握することが、第一歩です。研究計画書は、すぐに作成できるものではありません。出願の締め切りを念頭に置いて、余裕をもって作成を始めましょう。
2.研究計画書の形式
心理学論文を読んだことがない方は、まず実際の論文に軽く目を通してみてください。Google Scholar、CiNii Research、J-STAGEなどから、興味のあるキーワードを検索できます。
心理学論文は基本的に、タイトル、問題、目的、方法、結果、考察、引用文献という構成です。しかし、実際に大学院へ入学してから研究を始めるため、研究計画書の段階ではタイトル、問題、目的、方法、引用文献のみを書くこととなります。研究計画書の字数は、大学院によって異なるため、これも志望校の募集要項で確認してください。ここまでが研究計画書の形式的なお話となります。
3.研究計画書の作成手順
ここからは私自身の経験に沿って、研究計画書の作成手順を紹介します。必ずしもこの手順を踏まなければならないということではありません。参考になる部分があれば、取り入れてみてください。
まずは研究でざっくりと扱いたい対象であるテーマを決めましょう。そもそも、なぜそれを扱いたいのかということも考えてみると、よりしっかりとした研究計画書の基盤ができると思います。当通信では、例として「不登校」をテーマとした場合の例を紹介します。先行研究等は省略しますが、実際の研究計画書では、自身の主観を書くのではなく、主張を裏付ける先行研究やデータを示すことが必要となるため、注意してください。
次に、そのテーマは現在どんな状況なのでしょうか?逆に、理想はどうなることでしょうか?例えば、不登校は年々増加しており、いまだ解決策が見いだせない状況です。ただし、不登校は登校することだけが目標ではなく、不登校児童が社会的に自立することを目標にして支援する必要があります。つまり、不登校を経験したその先の自立を見据えることが、重要だと考えられます。そこで、不登校を経験した方が、その経験に対し、なんらかの意味づけを行い、受容することが理想の状況であると言うことができるでしょう。
では、理想に近づくために解決すべき問題や課題【問題】はなんでしょうか?例に基づき考えると、不登校の事例はたくさんあるものの、その予後に着目した先行研究が少ないことが問題と言えるかもしれません(実際に予後に着目した先行研究が少ないor見当たらないということを提示できた場合です)。
そこで、問題解決のために何をどうするのかの案【目的】を考えてみてください。例えば、不登校経験者の中で、過去を受容できていると表現される方々を集め、不登校経験を受容するまでのプロセスを検討することで、前述した問題を解決することができると考えられます。
ここまでくれば、あとは研究の方法【方法】を考えるだけです。誰に、何を、どのように研究を実施するかは、最低限研究計画書に書いてください。実際の研究では、いつ、どこで、なぜこの方法を用いるのかまで考える必要があります。前述した例であれば、仮説生成型の研究となるため、実際に不登校を経験しながらも、現在就学または就労している方々を対象にしたインタビュー調査が適していると思われます。具体的な分析方法としては、GTA(グラウンデッド・セオリー・アプローチ)、TEM(複線径路・等至性モデル)などが使えそうです。
また方法を考える際は、研究を行うことによる調査対象者へのリスクや、そのリスクをできる限り低減させる対処といった倫理的配慮についても考えることが必要です。実際に研究を実施できるフィールドがあるのかどうかなどの実現可能性も視野に入れなければなりません。
上記までの作業が終われば、実際に研究計画書を書いてみてください。心理学論文を書く際は「、」ではなく、「,」を使用するなどのお作法があるため、日本心理学会の「執筆・投稿の手引き」が参考になると思います。そして、主張を裏付けるために引用した先行研究やデータを、最後に【引用文献】として示すことを必ず忘れないでください。
さて、いかがでしたでしょうか?研究計画書を作成するのは、なかなか大変だと感じられた方もいらっしゃるかもしれません。加えて、研究計画書は提出したら終わりではなく、面接時に面接官から質問を受けたり、口頭で研究計画書の説明が求められたりすることが一般的であるため、そこまで対策することが必要です。
研究計画書をどう書いていいのか分からなくなってしまったときや、面接対策として想定問答の準備をしたいときは、ぜひチューターカウンセリングを活用してください(もちろんその他のことでも問題ありません)。皆さんのご利用をお待ちしております!

