心理・チュートリアル通信「研究計画書について」
2025年度
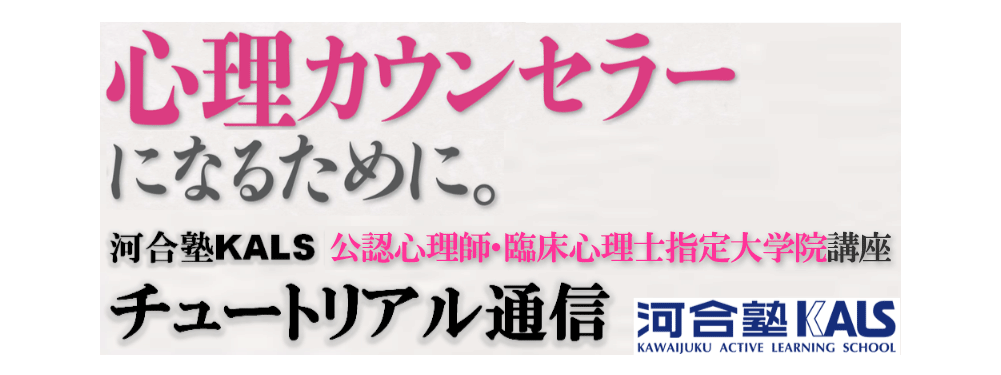
チュートリアル通信では、大学院に合格したKALSのチューターが、勉強法や参考図書、研究計画書について、各大学院の様々な情報や、心理士事情など皆さんに有益となるようなコンテンツをお送りしていきます。日々の勉強の合間の息抜きとして、是非ご覧になってみてください。
「研究計画書」について
名駅校チューター:村木
こんにちは、名駅校チューターの村木です。
みなさん,研究計画書の作成は順調に進んでいますでしょうか?すでに順調に進んでいるという方、どうしたらよいか分からず迷っている方、様々な方々がいらっしゃると思います。
そこで、今回のチュートリアル通信ではそんな「研究計画書」について、まずはどういうものなのか、お話ししたいと思います。そしてテーマの決め方や実際の作成方法などを、私の体験談を踏まえてお伝えします!
1.研究計画書とは?
まず、研究計画書とは、自分が大学院でどんな研究をしたいのかを明確に伝えるものです。自分自身が行いたい研究の問題・目的、仮説、研究方法などを詳しく書いたものになり、研究の論理性や実現可能性、先行研究との関連、研究の背景や意義などをまとめていくことが必要となります。大学院入試では、出願した研究計画書をもとに受験生に対して面接が行われることが多いので、そうした点でも重要なものになってきます。(研究計画がそのまま修士論文にならないことはあります。)
2.研究テーマの決め方
研究計画を作成するにあたって難しいのがテーマを決めることだと思います。私も実際に研究計画を作成するにあたって、自分が大学院で何をしたいのかずいぶんと悩みました。そんなときに、私が実践していたのは自分が最初に心理職を目指したきっかけ、初心に戻って考えてみることでした。
みなさんは、公認心理師や臨床心理士を目指して大学院入試の勉強を始めていると思います。そこで、なぜ公認心理師・臨床心理士になりたいのか、どのような領域で心理職を目指したいのか、今一度考えてみてください。自分がどんなことに興味や関心を持って心理職になろうと思ったのか、そしてそのためには自分が何を研究したいのか、そうしたことを考えていく中で、研究テーマやヒントが見つかるかもしれません。
(ちなみに私は「青年期の適応と家族機能について」検討したいと思いました。)
3.作成方法
研究テーマが決まったら、実際に研究計画の作成に進みます。テーマにはいくつかのキーワードがあると思うので、それらの先行研究を調べていくことが必要となってきます。それらのキーワードを組み合わせながら先行研究を調べていくのですが、もしかしたら自分がやりたい研究がすでに行われていることがあるかもしれません。しかし、そこで諦めてはいけません!そうした研究でも、考察の中に課題や問題点が記されていることがあるので、そこから新たに考えていくことも、研究計画を作成する一つの方法だと思います。
(先生やまわりの人にもたくさん相談して、作成していきましょう!)
以上のように、今回は「研究計画書」をテーマにお話ししてきました。
KALSでは、先生から直接「研究計画の指導を受けることができる」ので、テーマ決めから完成まで専門的なアドバイスをもらうことができます。ぜひ活用してみてください!
とはいっても、研究計画の作成を進める中で、不安になることや自信がなくなるときがあると思います。そんなときは、ぜひチューターとのカウンセリングを予約してみてください。みなさんのご相談に乗ることで、一緒に大学院入試を乗り越えることができたら嬉しいです!

