心理・チュートリアル通信「研究計画書について」
2025年度
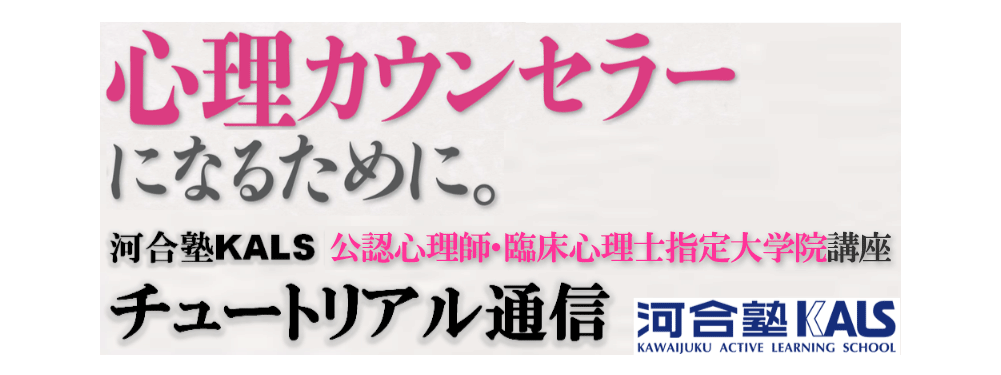
チュートリアル通信では、大学院に合格したKALSのチューターが、勉強法や参考図書、研究計画書について、各大学院の様々な情報や、心理士事情など皆さんに有益となるようなコンテンツをお送りしていきます。日々の勉強の合間の息抜きとして、是非ご覧になってみてください。
🌷研究計画書について🌷
名駅校チューター:梶田
こんにちは。名駅校チューターの梶田です。
みなさん,そろそろKALSの授業には慣れてきたでしょうか?
授業だけでなく,チューター相談もぜひ利用してくださいね。お待ちしております♪
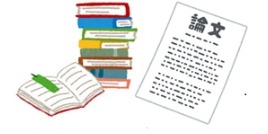
さて,今回のチュートリアル通信では,研究計画書についてお話ししていきます。
早速ですが,みなさん,研究計画書の執筆は順調に進んでいますでしょうか?順調に執筆が進んでいる方,まだ着手していない方,迷っている方など…様々な方がいらっしゃると思います。
今回は研究計画書の執筆に関して,①研究計画書について考える,②心理学研究について知る,③研究計画書の始め方という3点についてお話ししていこうと思います。
①研究計画書について考える
まずはみなさん,研究計画書についてどのような認識をされているでしょうか?私は,研究計画書は「第一印象」であると考えています。
研究計画書は出願の際に,志望校に提出しますよね。そう考えると,実は研究計画書は,「志望校に最初に届く受験生に関する情報」なのです。つまり,志望校からすれば,研究計画書が受験生に対する第一印象となるのです。みなさん「第一印象が肝心!大事!」とこれまで何度も聞いてこられたと思います。そう考えると,「研究計画書って結構重要なポジションだな…」と思いませんか?
そんな第一印象とも言える研究計画書ですが,大切なこととしてまずは絶対にミスがあってはならない!当たり前のことですが,提出後に誤字脱字を見つけてしまった…というケースは毎年見られるのではないかと思います。友達や先生に読んでもらったり,Wordの音声読み上げ機能を使って確認したりするなど,誤字脱字のチェックをすることを習慣づけていきましょう。これは心理学の試験においても重要なことです。
②心理学研究について知る
みなさんは心理学研究について,十分に理解できていますか?
基本的に「問題・目的→方法→結果→考察」という流れで進んでいくことはもちろんですが,心理学研究におけるルールや,臨床心理学における研究の社会的意義についてはご存じでしょうか?
当たり前ですが,研究計画書は心理学に関する研究です。そのため,研究計画書の執筆は,心理学研究のルールに従う必要があります。心理学研究においては,「執筆・投稿の手びき」というルールブックが存在します。図の挿入や文献の引用の仕方などは「執筆・投稿の手びき」に従うことが原則です。きちんと心理学研究のルールを理解しているかということは,大学院の先生方がチェックする点の1つなのではないかと思います。知らなかったという人は,「執筆・投稿の手びき」を確認しながら研究計画書を執筆していきましょう。
(「🔍心理学 執筆・投稿の手びき」と検索すれば閲覧できます。)
また,臨床心理学における研究の社会的意義について,「その研究が臨床心理の現場においてどう役立つか」ということを考えなければなりません。心理学研究は,人の心を対象としています。そのため,人に協力していただかないと研究を行うことができません。このように,人様に協力していただいたからには,やはりその人達に,なにか還元できるような社会的意義が必要になるのです。
多くの人に協力していただくということは,多くの人に負担をかけてしまうということでもあります。ただ単に,自分が気になるからだとか,面白そうだからという理由では,多くの人に負担をかけてしまっただけになってしまうのです。臨床心理学を研究する者として,協力していただいた人達に対して,臨床心理学的にどんなことを還元できるだろうか,どんなことに役立つだろうかということを考えることが,今後臨床心理学を学ぶ大学院生になるみなさんに求められる姿勢なのではないかと思います。研究計画書を執筆する際は,この点について一度立ち止まって考えてみてください。
③研究計画書の始め方
最後になりますが,いよいよ研究計画書の始め方についてです。「研究計画書っていつから取り組めばよいのだろう…」と悩んでいる方も多いのではないかと思います。結論から申し上げますと,まだ取り組み始めていない人は,今日から始めていきましょう!
「そんないきなり今日から始めるなんて無理!」と思われるかもしれませんが,大丈夫。最初は小さなことからでよいのです。自分が気になっていることを紙に書き出してブレインストーミングをしてみたり,気になるキーワードで論文を検索したり,書籍や論文を読んでみたりなど…まずは,自分の興味のあることや行いたい支援について考えてみることから始めてみてください。
これは私の個人的な感覚ですが,研究計画書の執筆においては,「自分がやりたいことを見つけること」に最も時間がかかります。やりたいことというのは,急に降ってくるものではありませんからね…実際に研究計画書を書き始めるのはもっと後でも構いません。でも,自分が興味のあることや行いたい支援について考えることは,早め早めに始めていきましょう!それが今後の研究計画書執筆に必ず繋がってくるはずです。
KALSの小テストなら一夜漬けでもなんとかなるかもしれませんが(本当はダメですよ…コツコツ勉強しましょう!),研究計画書はそうはいきません。まずは小さなことからでも,1日30分だけでもよいので,まずは“始めてみること”からやっていきましょう!

